ベランダ菜園といえば、まず思い浮かぶのが「ミニトマト」ではないでしょうか?
プランターでも育てやすく、真っ赤に色づいた実を収穫する喜びは格別です。
ミニトマトの栽培は、初心者さんにも挑戦できます。
大玉トマトに比べて少ないスペースでたくさん実がつくため、ベランダでも育てやすい野菜です。
 初心者さん
初心者さんでも、育てるのって難しそう…ベランダでも本当にできるかな?



大丈夫です。
ポイントを押さえれば、初心者の方でもベランダで手軽に美味しいミニトマトを栽培できますよ!
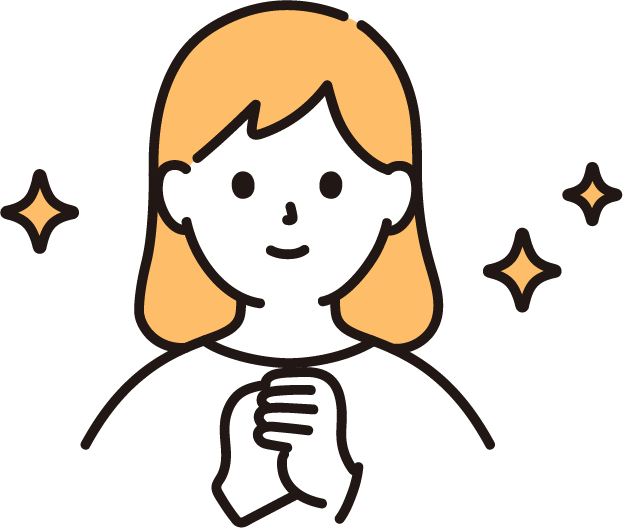
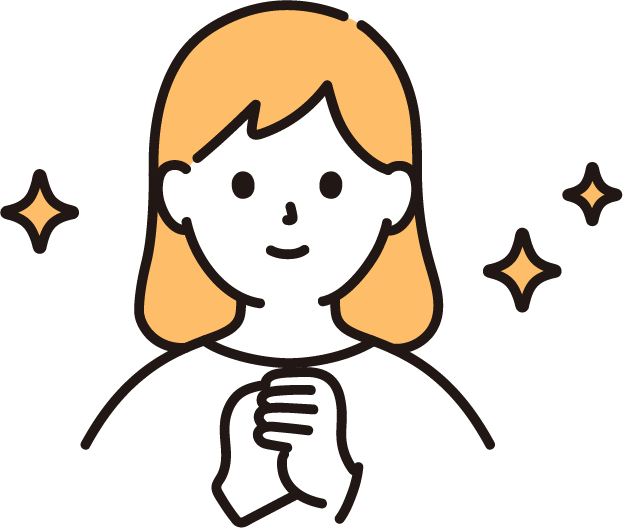
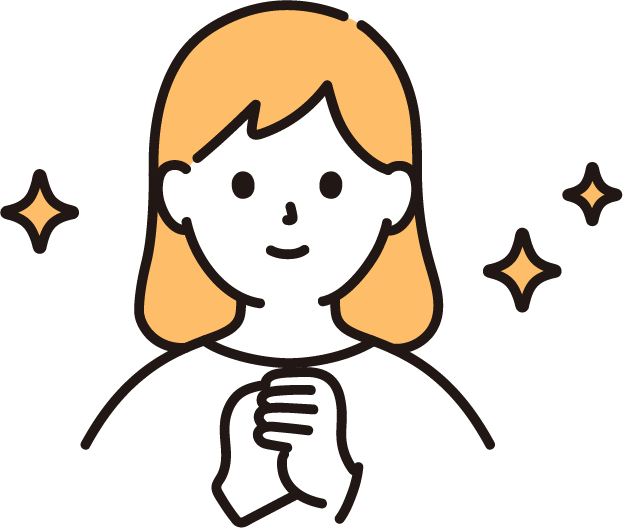
それなら挑戦してみたいです!
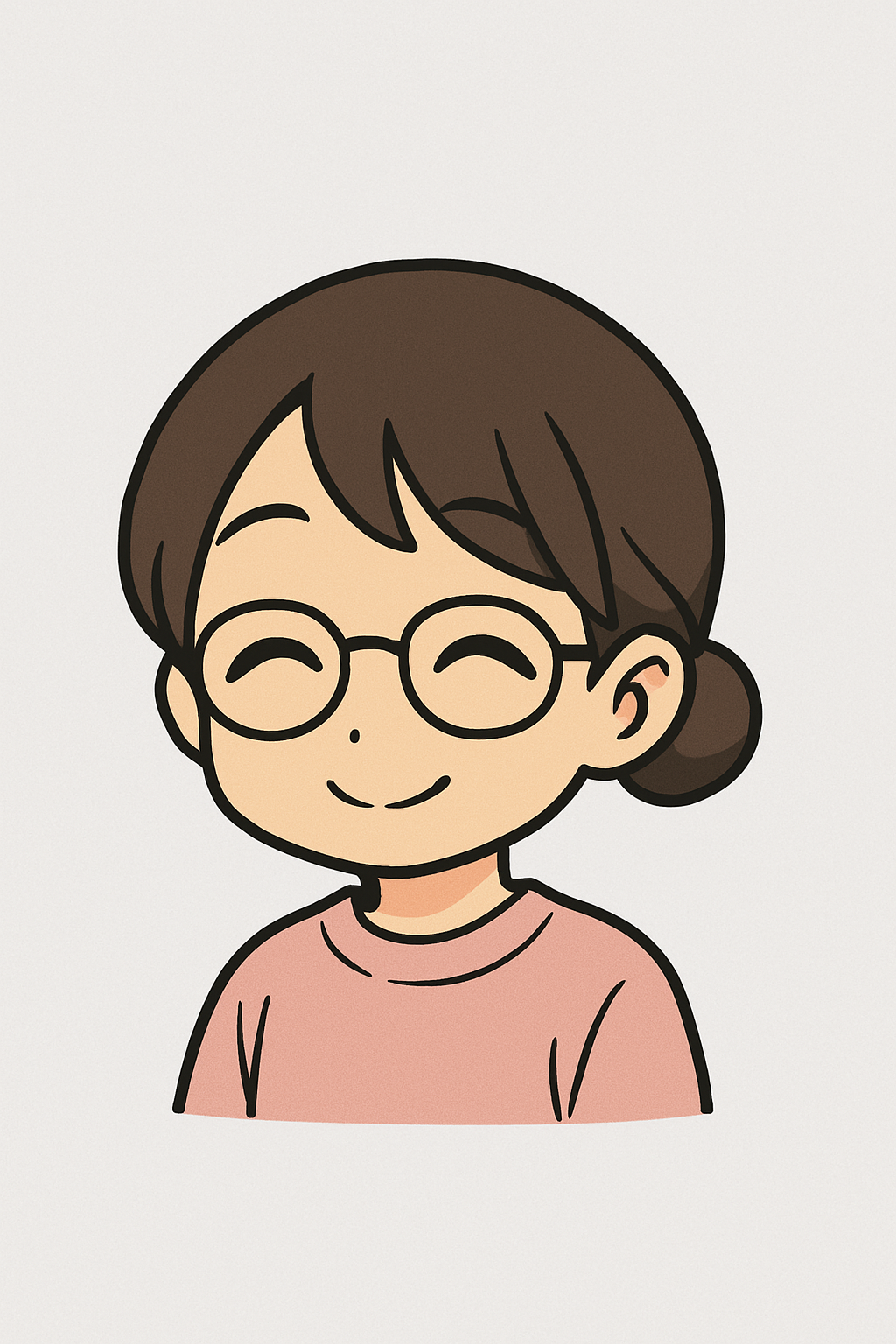
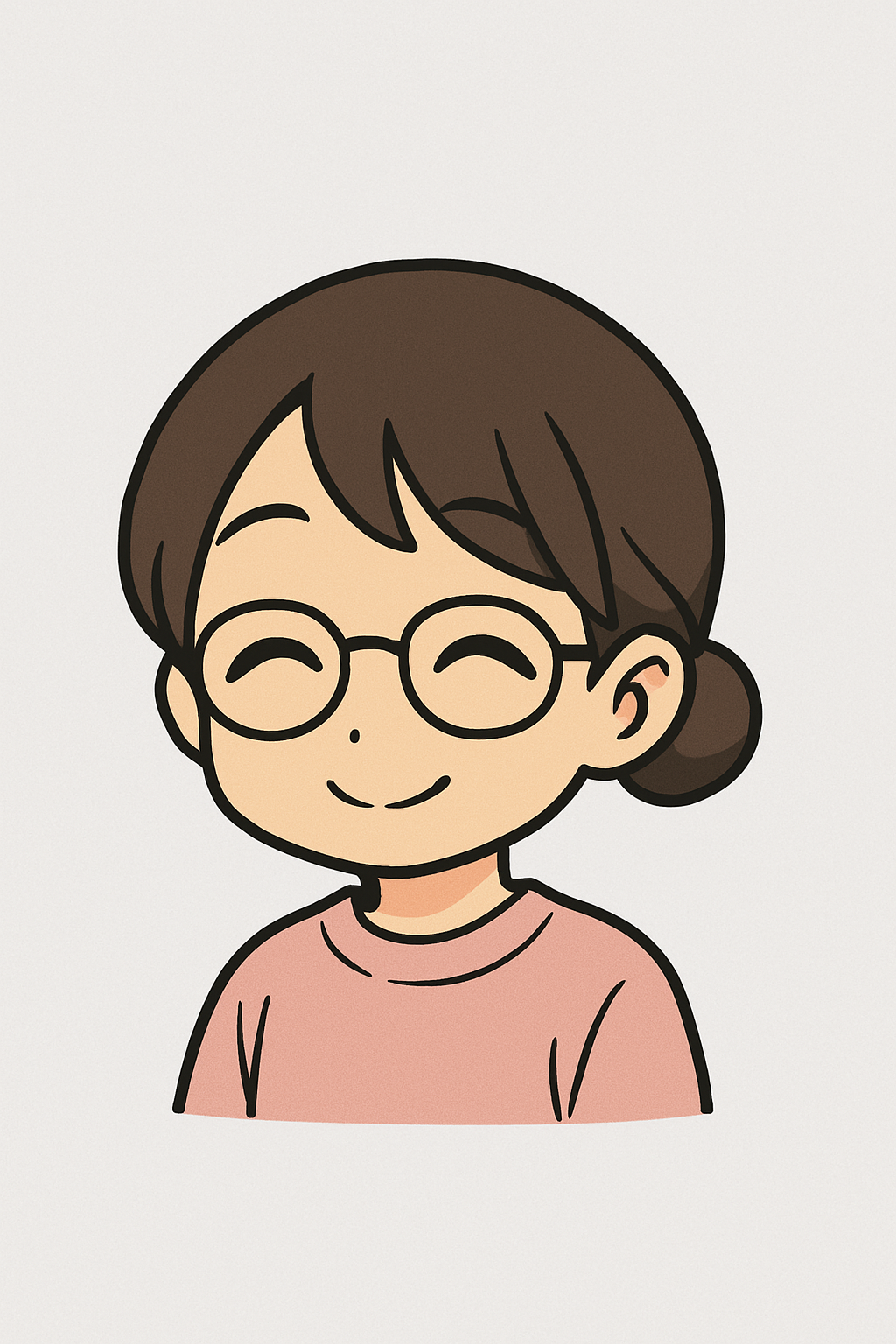
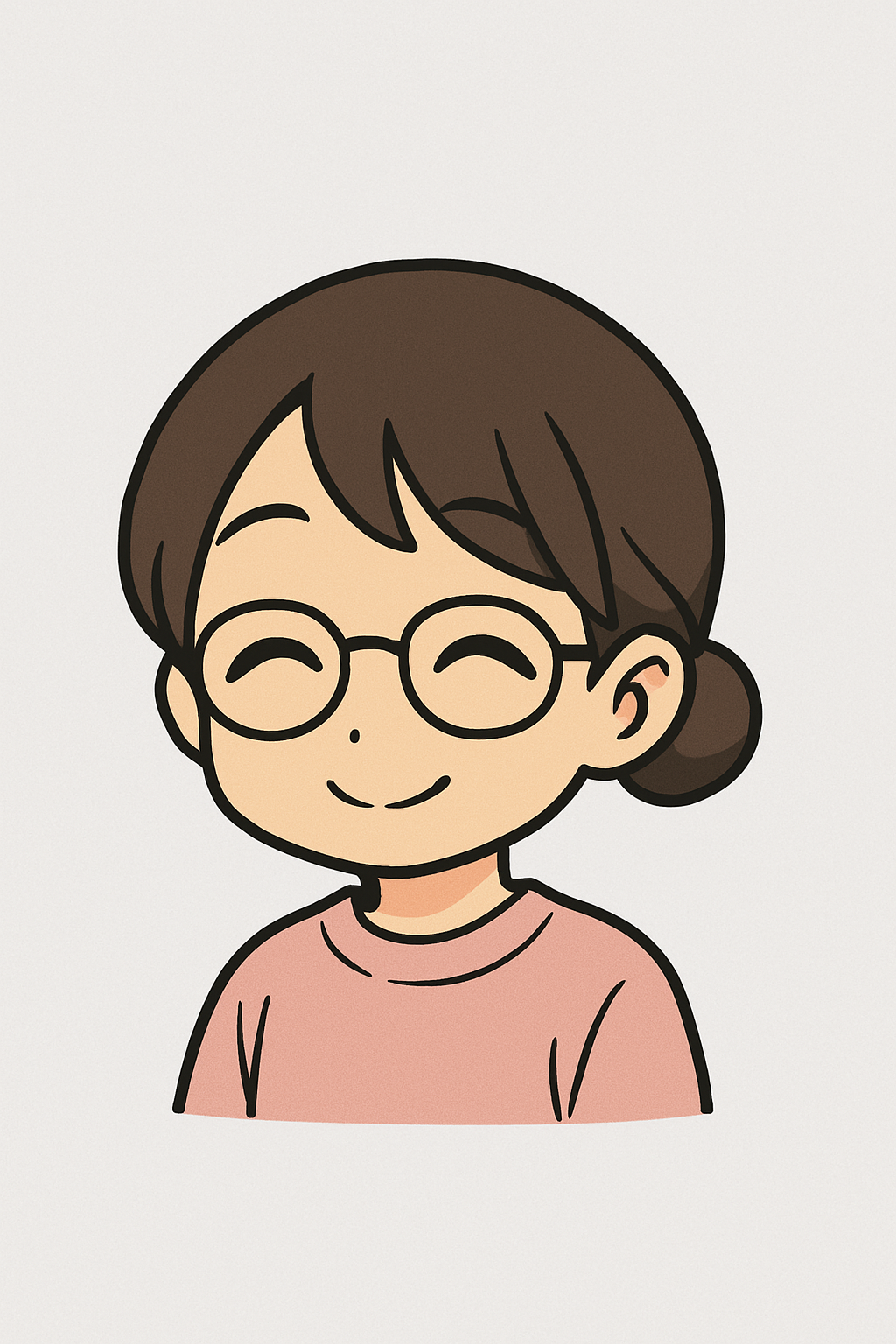
ぜひ、一緒にやってみましょう!
ミニトマトの育て方をくわしく解説していきますね。
春から夏にかけては、野菜栽培を始める方が多い季節。
この記事では、ミニトマトのプランター栽培に必要な必要な道具・資材から、品種の選び方・植え付けのタイミング・日々の管理方法まで、写真や図表を交えて解説します。
自分で育てた採れたてのミニトマトの味は、スーパーで買うものとは一味も二味も違います!
ぜひこのガイドを参考にして、ベランダ菜園の第一歩を踏み出してみてください。
さあ、ご一緒に!ベランダでミニトマト栽培を始めましょう。
- この記事では、ミニトマトの育て方を初心者の方向けに詳しくご紹介しています。
長めの内容となっていますので、目次から気になる項目をクリックしてご覧ください。
画面右下のマークで、記事上部に戻ります。
ミニトマトはどんな野菜?
ミニトマトの特徴と魅力
ミニトマトは、大玉トマトや中玉トマトと同じく、南米アンデス高原が原産の野菜です。16世紀にスペイン人によってヨーロッパに、17世紀頃には唐なすびや唐柿として日本に伝わりました。
「ミニトマト」とは、10グラムから30グラムほどの小さなトマトを指し、それ以上の大きさのものは中玉や大玉に分類されます。赤色以外にも、黄色、オレンジ色、緑色、チョコレート色など、さまざまな色の品種があるのが特徴です。
ミニトマトの栽培は、生育が旺盛で着果が比較的安定しているため、初心者にも取り組みやすい作物とされています。実が割れにくく、多少放任していても健康に育ってくれる傾向があるため、大玉トマトで失敗した経験がある方にもおすすめです。
また、ミニトマトは次々と実が鈴なりにでき、見た目にも楽しく、長期間の収穫を楽しめることも大きな魅力です。
ミニトマトの基本データ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 学名 | Solanum lycopersicum |
| 和名 | ミニトマト・プチトマト |
| 分類 | ナス科トマト属(多年草/日本では一年草扱い) |
| 特徴 | 果実が小さく甘味が強い・家庭菜園でも人気・品種により草丈に違いがある |
| 連作障害 | あり(ナス科の連作は2〜3年あける) |
| 土壌酸度 | pH6.0~6.5 |
| 栽培時期 | 4月〜9月(苗の植え付けは4〜5月) |
| 成育適温(気温) | 10~30℃(発芽・生育に適する) |
| 発芽適温(地温) | 20~25℃ |
| 種の光発芽性 | 嫌光性種子(光を嫌う) |
| 種のまき時 | 2〜3月(育苗用トレイなどで室内管理) |
| 発芽までの日数 | 7~14日(温度条件により変動) |
| 苗の植え付け時期 | 4月下旬〜5月中旬 |
| 収穫時期 | 6月〜8月(早ければ5月下旬から) |
| 収穫まで | 植え付け後、約50日〜 |
| 品種例 | 千果、アイコ、レジナ(矮性)、マンマミーア(中高性) |
| 草丈 | 矮性:30〜60cm / 中高性:1.5〜2m以上(品種により差) |
| 日当たり | 日当たりの良い場所(1日6時間以上が望ましい) |
| 耐暑温度 | 35℃前後まで生育可能(真夏の管理に注意) |
| 耐寒温度 | 2℃(霜に当たると枯れる) |
| プランターサイズ | 10号鉢(10〜12L)、または60サイズ深型(60×30×30cm以上) |
| 株間 | 30〜40cm |
| 病害虫 | アブラムシ、タバコガ、ハモグリバエ、サビダニ |
| 栽培ポイント | 日当たり・水はけのよい土を選び、支柱と誘引で茎を支える。わき芽かき・摘心・追肥のタイミングが収量アップの鍵。 |
ミニトマトの品種:最初の「品種選び」が成功の鍵


ミニトマト栽培を成功させるには、適切な品種を選ぶことが非常に重要です。
たくさん収穫したい、柔らかい果実を収穫したい、コンパクトに育てたいなど、ご自身の栽培環境や、どのようなミニトマトを収穫したいかに合わせて選びましょう。
ベランダ菜園におすすめのミニトマト品種
千果(ちか)

色々な品種を育てた中で、私が1番おすすめできる品種です。
育てやすさ、収穫量、甘さや酸味など、全てのバランスが整っていて、ベランダ菜園に向いていると思います。
2025は夏野菜の栽培に出遅れてしまったため、来年からまた栽培を開始しようと思っています。
特徴
- 小さく丸い濃赤色で、美しい光沢を持つ、ミニトマトといえばこれ、という見た目
- 極早生種で、糖度は8~10度と安定しており、味のばらつきが少ない
- 草勢(株の成長の勢い)が強すぎず弱すぎず中強で、管理しやすい
- 収穫量も多いため、少ない株数でも十分に栽培を楽しめる
- 耐病性にも優れているため、家庭菜園から商業栽培まで幅広く利用されている
- 日本のミニトマト栽培で非常に高いシェアを持つ代表的な品種で、「スーパーでよく見かける普通のミニトマトは千果」と言われるほど流通量が多い
アイコ

私が一番最初に育てたミニトマトです。
丈夫で育てやすく、収量も多いです。
裂果しにくいですが、家庭菜園で栽培したものは、お店で販売されているものよりも皮が硬めになることがあります。
黄色のアイコの方が、赤いものよりもさらに味が良いと感じます。
特徴
- 縦長の卵型で、スリムな形
- 糖度は9~10度と高く、甘みが強く果肉感のある食感が特徴
- 愛らしい名前と見た目。スナックのようにも食べることができ、その上美味しい
- 平成になって初登場して以来、今では店頭でもよく見かけミニトマトの新しい定番品種
品種を選ぶ際には、病害虫に強い品種や、地域の気候条件(耐寒性・耐暑性)に合った品種を選ぶことも重要です。
「矮性ミニトマト」:狭いベランダにもおすすめ
矮性(わいせい)ミニトマトとは、草丈が低くコンパクトに育つ品種のことで、以下のようなメリットがあります。
矮性(わいせい)ミニトマトのメリット
- 支柱が不要、または短い支柱で対応できる
- ベランダや狭いスペースでも省スペースで育てられる
- 小さな鉢でも栽培可能なので、子どもや初心者にも人気
草丈があまり高くならない「矮性品種」は、支柱がいらない・わき芽かき不要など手間が少なく、特に初心者におすすめです。横に広がるように成長し、倒れにくいため、風の強いベランダでも安心して育てられます。また、省スペースで育てられるので、複数の野菜を並べて育てたい方にもぴったりです。
矮性ミニトマトは、草丈がコンパクトで初心者にも育てやすい特徴を持つ品種群です。支柱が不要だったり、わき芽かきの手間が少なかったりと、省スペース&低管理で育てられるのが最大の魅力です。
以下のような品種が代表的です。
主な矮性ミニトマトの品種例
レジナ

矮性品種の代表格です。
観賞用として開発された背景から、「甘みが弱く、酸味が強い昔ながらのトマトの味」とされていました。
最近では「糖度8~10」と表示された苗も流通しており、味も「甘い」との評価もあり、育て方も影響するようです。
特徴
- 草丈が20〜30cmほどと非常にコンパクトな矮性品種
- 室内やベランダでも育てやすい
- 支柱が不要なうえ、わき芽もあまり出ないため、初心者向け
- 果実は小さめで、皮が薄く甘みがあり、食べやすい味わいが特徴
- 見た目も可愛らしく、観賞用としても人気
マンマミーア

名前に惹かれて購入した「マンマミーア」の種。最初は他の品種に良い場所を譲り、試しに育ててみました。
猛暑の直射日光やエアコン室外機の熱風が当たる過酷な環境、6号という小さめの鉢で、遅めの4月中旬に種まきからスタート。
その結果、ほとんど手をかけられなかったにもかかわらず、2鉢で73個、収穫できました。
ただし、皮がかなり硬く、味も思ったほど美味しく仕上がりませんでした。
今年(2025年)は、引っ越し先の日陰のベランダで再チャレンジ中。
よりおいしく育てられるよう、現在も試行錯誤を続けています。


特徴
- 草丈80〜120cmほどとやや大きめ
- 比較的コンパクトな範囲に収まる矮性寄りの品種
- 多収性で、1つの房に20個以上の実をつけることもあり、たっぷり収穫したい人に向く
- 果実はやや縦長で、甘みが強く酸味が控えめ
- 肉厚でしっかりとした食感があり、生食にも加熱調理にも適している
このような品種は、支柱や大きなプランターが用意できない環境でも育てやすく、初めてのミニトマト栽培に特におすすめです。
ミニトマトの苗


ミニトマト栽培は「苗」から始めるのが簡単でおすすめです。
ミニトマト「苗」の選び方:元気な主役を選ぶ!
苗は、4月中旬から5月頃にかけて園芸店やホームセンターに出回ります。最近は温暖化の影響もあり、早くから販売が開始されることも多いです。
以下のポイントをチェックして、元気な苗を選びましょう。
- 茎が太くてしっかりしている
ひょろひょろと細長いものは避ける - 節と節の間が詰まっている
間延びしていない、がっしりとしたもの - 葉の色が濃く、厚みがある
黄色っぽい葉や、病害虫の跡がないか確認 - 一番花(最初の花)が咲いているか、蕾がついている:
実付きが良い苗のサイン
品種
初心者の方は、「病気に強い」「育てやすい」と書かれた品種を選ぶと安心です。「アイコ」や「千果(ちか)」などが人気です。
ミニトマトの苗には、病気に強く育てやすい「接木苗(つぎきなえ)」と、比較的安価な「実生苗(みしょうなえ)」があります。
接木苗と実生苗:初心者さんは接木苗がおすすめ
ミニトマトの接木苗と実生苗の違い
接木苗と実生苗は、野菜の苗の作り方や特性に違いがあります。
それぞれの特徴、メリット・デメリットをまとめます。
接木苗(つぎきなえ)とは
異なる2つの苗(台木と穂木)をつなぎ合わせて作る苗。台木(根になる部分)は病気や環境ストレスに強い品種、穂木(茎や葉・実になる部分)は味や品質の良い品種が使われます。
- 病気や連作障害に強い(台木の特性による)
- 環境ストレス(高温・低温・乾燥など)にも強い
- 収穫期間が長く、収量も多くなる傾向
- 農薬の使用量を減らせる場合がある
- 価格が高い(実生苗の2~3倍)
- 自分で作るには技術と手間が必要
- 台木から芽が出た場合の管理が必要(芽かき)
- 接木部分が傷つくと苗が枯れるリスクがある
実生苗(みしょうなえ)とは
種からそのまま発芽・育成した苗。自根苗(じこんなえ)とも呼ばれます。
- コストが安い(接木苗よりも2~3倍安価)
- 大量生産が可能で、ホームセンターなどで多く出回っている
- 親株の遺伝子をそのまま受け継ぐ
- 品種の選択肢が多い
- 病気や連作障害に弱い
- 環境変化やストレスに弱く、育苗管理が難しい場合がある
- 収穫量や収穫期間は接木苗より劣る傾向
比較表:接木苗と実生苗
| 項目 | 接木苗(つぎきなえ) | 実生苗(みしょうなえ) |
|---|---|---|
| 作り方 | 台木と穂木を接ぐ | 種からそのまま育てる |
| 病気・連作障害 | 強い | 弱い |
| 環境ストレス | 強い | 弱い |
| 収穫量・期間 | 多い・長いことが多い | 少なめ・短め |
| 価格 | 高い | 安い |
| 管理の難易度 | 高い(技術・管理が必要) | 比較的容易 |
| 品種選択 | 台木・穂木の組み合わせが必要 | 豊富 |
どちらを選ぶべき?:苗を選ぶときのポイント
- ミニトマトを初めて栽培
- 土を使い回す
- 病気が心配
- コストを抑えたい
- 品種にこだわりたい
- 病気や連作障害のリスクが低い環境
このように、栽培環境や目的、予算に応じて選びましょう。
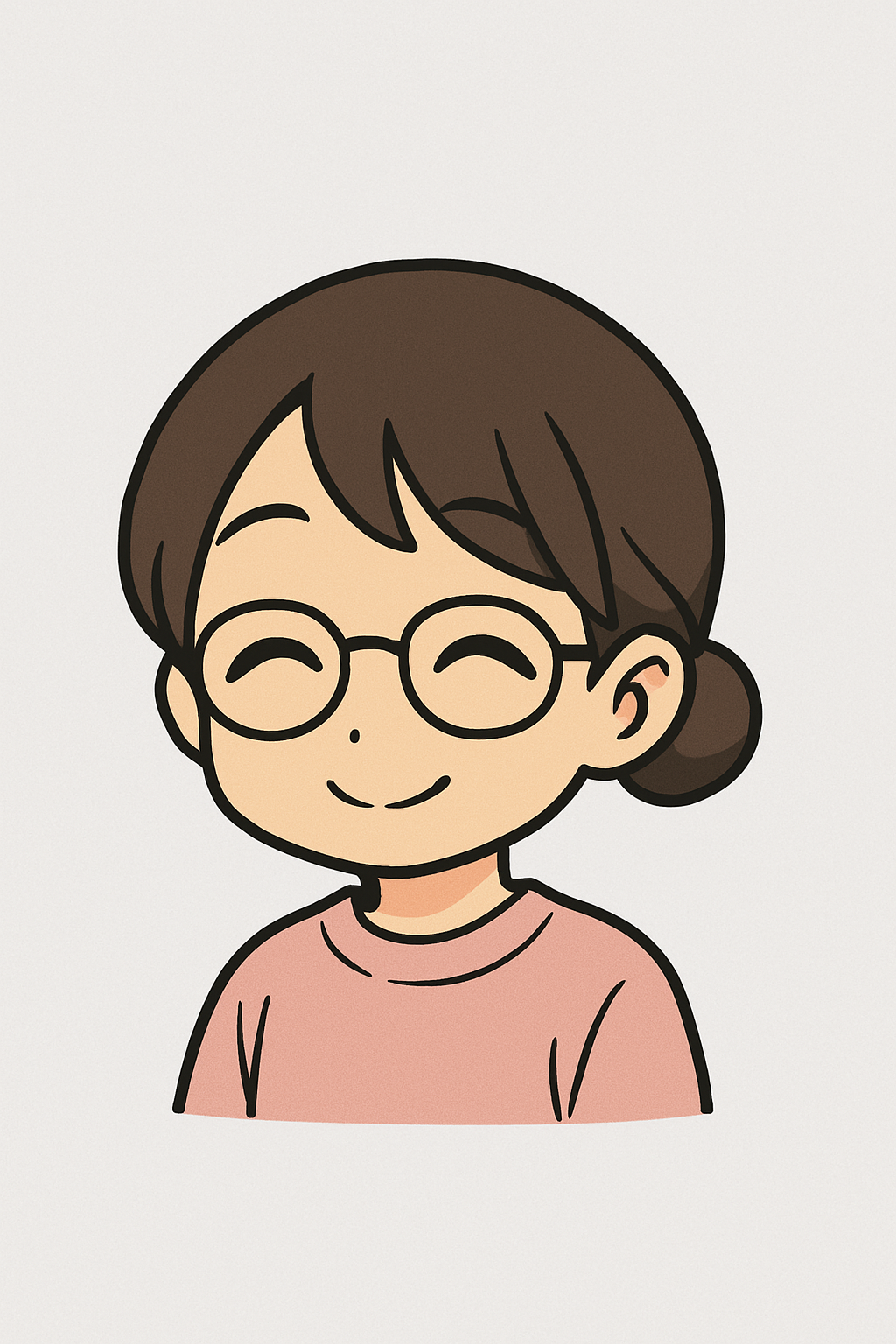
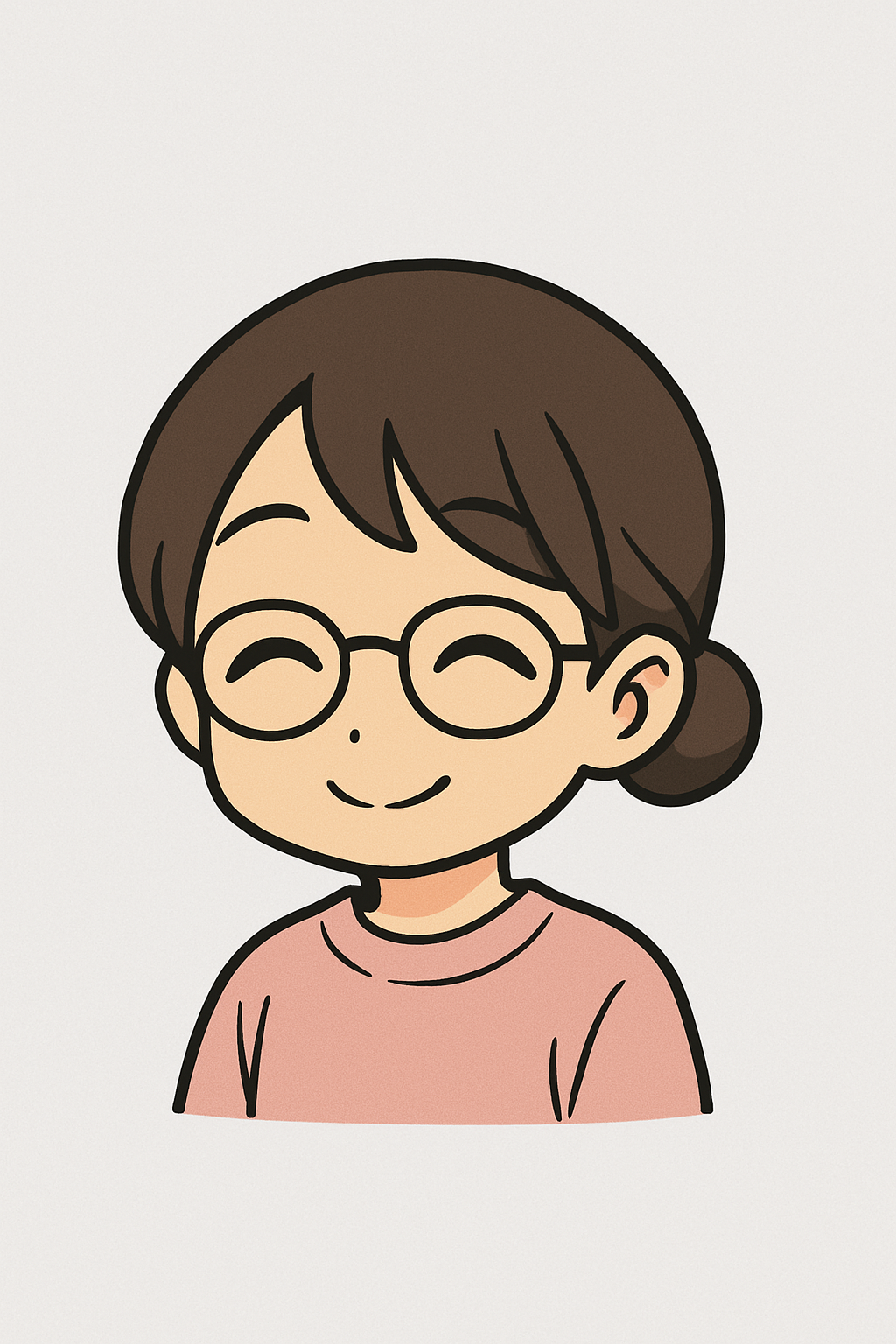
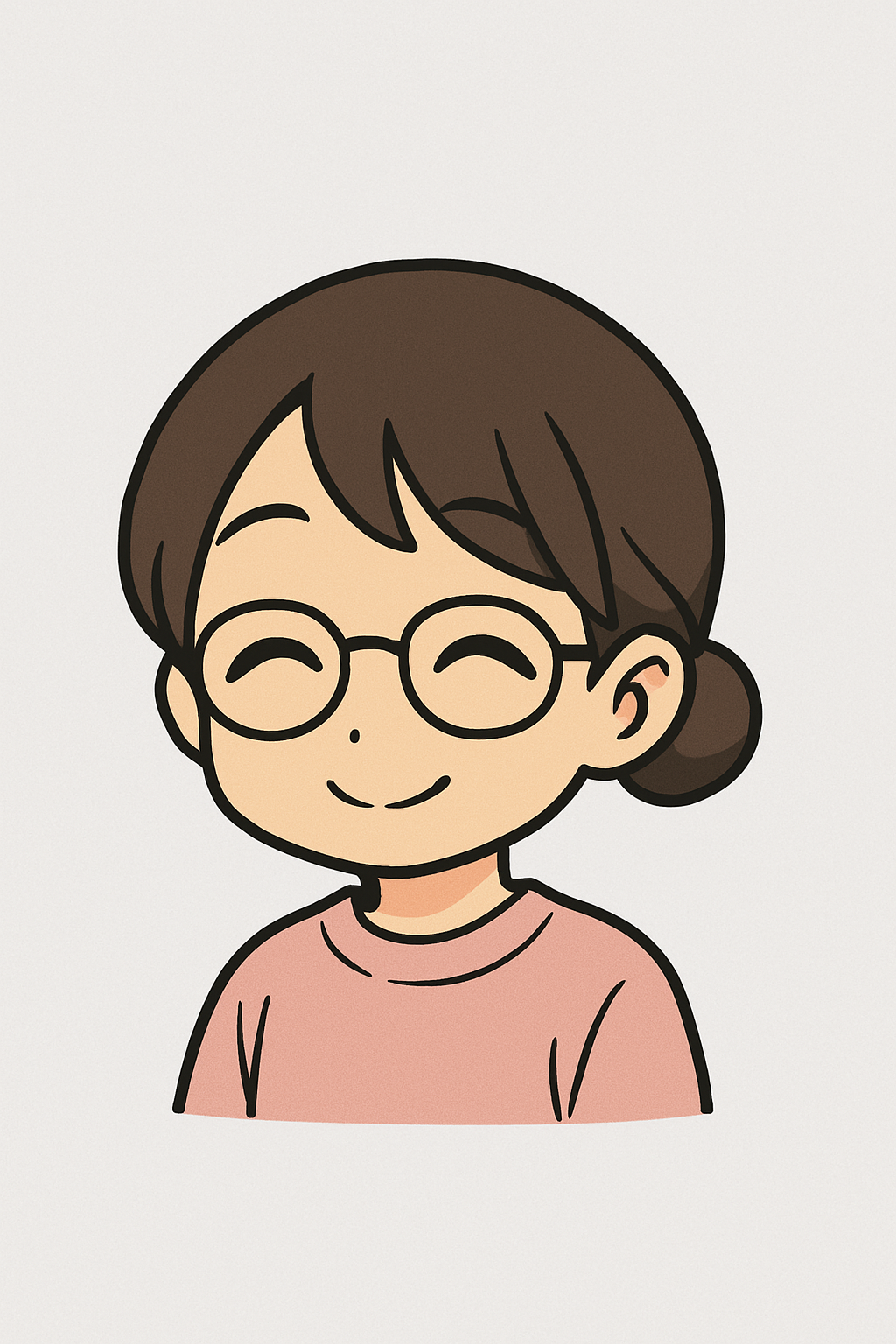
初心者の方は少し値段が高くても接ぎ木苗を選ぶと失敗が少ないでしょう。
慣れてくると、自分で種をまいて苗を作ることもできるようになります。
私自身、ミニトマトは、種から育苗をして栽培できるようになりました!
園芸家 深町貴子さんプロデュースの矮性タイプ。11月以降も室内窓際などで一年中栽培可能。
その他の道具・資材など:栽培を始める前に用意するもの
ミニトマト栽培には他にもいくつかの資材などが必要です。栽培を始める前に、適切な土や資材も準備しておくと、慌てずにすみます。
土やその他の資材は、ホームセンターや園芸店、インターネットの店舗でも手に入ります。
ミニトマト栽培の「土」:野菜用培養土がベスト!
初めてミニトマトを育てる方は、市販の「野菜用培養土」を使うのが最も簡単で確実です。
- 肥料が最初から配合されている(元肥入り)ものを選ぶ
- ミニトマトの成長にも必要な栄養素が含まれている
- 雑草の種や病害虫の混入リスクを大きく下げることができる
古い土の再利用は病害虫のリスクがあるので、始めのうちは新しい土を使いましょう。
\土の選び方は、こちらの記事も参考にしてください/


ミニトマトの「プランター」
ミニトマトは根をしっかり張るので、ある程度の大きさが必要です。
ミニトマトは根を深く伸ばし、たくさんの実をつけるため、深さが30センチ以上ある鉢やプランターを選ぶのがおすすめです。スペースに余裕があれば、より大きいものを選ぶと地植えに近い環境で育てることができます。
サイズ
- 深さと直径がそれぞれ30cm以上、容量15L~25L程度のものが目安
- 1つのプランターに1〜2株植えるのが基本
- 深さがあると根がしっかり張り、乾燥にも強くなる
形状
- 丸型でも長方形でもOK、深さがあるものを
素材
- プラスチックやテラコッタ(素焼き)など
- 水はけと通気性が良いもの
- 集合住宅のベランダでは、重量に気をつける
初心者の方におすすめのプランター
鉢底の穴が開いている・横にスリットがあるものを選ぶと、水捌けがよく、特に生育初期の根腐れを防ぐ
スリット鉢は鉢底石を敷かないで使用します
深型のプランター 側面の穴を線で塞ぐタイプで、慣れてくると夏の水やりが楽
「鉢底石」と「鉢底ネット」
- 鉢底石
- 鉢底石
- 水やりの際の土の流出も防ぐ
- ベランダ菜園では、鉢の重さ軽減のため、軽いタイプの鉢底石がおすすめ
スノコ付きプランター
・鉢底石用ネット
- 鉢底石を鉢底石ネット
- 鉢底石とネットを別のものにしておくと、野菜や鉢によって鉢底石の量を調節することが可能
網目に根が入りにくい構造で、植え替え時の手間が削減できるものを使っています
成長をサポート!「支柱」と「紐」
ミニトマトは成長すると背が高くなるので、支えが必要です。
支柱
- 長さ150cm前後のものを1株につき1本〜3本(よりしっかり仕立てるには3本)用意
- 苗の成長に合わせて誘引していくので、ある程度の長さが必要
慣れてきたら「あんどん型支柱」を使用すると、台の上などでもコンパクトに育てることができます。
紐またはピンチ
茎を支柱に結びつけるための紐。
- 茎に食い込みにくい麻紐やビニール紐などがおすすめ
- 誘引専用のピンチでも可、100円ショップでも取り扱い有り
私は、大きめの洗濯バサミで代用することもあります。
⑥その他のお世話グッズ
移植ゴテ
苗を植えたり、プランターに土を入れる時に使用。
100円ショップなどでも手に入ります。
全長が約30cmのものが多いので、株間をはかったり、植え付け時などのちょっとした目安になります。
我が家は子供が幼稚園の頃「おいも掘り」に使ったものを今だに使っています。最近持ち手のキャップが外れるようになってしまいました。作業のたびに「いい加減、買いかえようかなぁ」が続いています(笑)。
ジョウロ
水やりに使います。
園芸店や100円ショップでも購入できます。
先端部分の「はす口」を取り外せるものが便利です。
日々使用するものなので、少し奮発して気に入ったデザインものを購入しました。
私は、このようなタイプの容量5Lを使用しています。
園芸用ハサミ
収穫・わき芽かき・茎葉の整理などに使います。清潔なものを使いましょう。
多くの園芸家さんに愛用されているクラフトはさみ
収穫後、野菜とともにキッチンで洗えるキッチンバサミも便利 分解可能・食洗機対応
肥料
追肥(ついひ・生育の途中で与える肥料)です。
- 液体肥料や固形肥料を用意
- ベランダでのプランター栽培には、水やりとともに追肥できる液体肥料がおすすめ
実践編:植え付けから収穫までのステップ
準備ができたら、いよいよ栽培スタートです!
その前に…。
苗を植えるには、少し早いかな、と感じる時があります。
その場合、以下の方法で短期間しのいで、時間をかせぎましょう。
植えつけ適期まで:鉢増しで育苗
まだ寒さの残る春先など、早くに購入した苗をすぐに植え付けるのが心配な場合には、暖かくなる植え付け適期まで、ひと回り大きい鉢に植え替える鉢増しをして自宅で引き続き育苗をする方法もあります。
人気の品種が売り切れる前に、苗を購入した場合などにも有効です。
植え付け:ゴールデンウィークを目安に
植え付けの時期:ゴールデンウィーク前後
遅霜の心配がなくなり、暖かくなるゴールデンウィーク前後(4月下旬~5月下旬頃)が植え付けの適期です。
植え付けの手順
- プランターの底に鉢底ネットを敷き、その上に鉢底石を入れる
- プランターの底が見えなくなる程度
- プランターの底が見えなくなる程度
- 培養土をプランターの8分目くらいまで入れる
- プランターには、ウォータースペースという線がついているものが多い
- その場合、ウォータースペースの線を目安に
- 土に、苗のポットと同じくらいの大きさの植え穴を掘る
- ポットに入れたまま、一旦苗を穴の部分に置いてみるとわかりやすい
- ポットに入れたまま、一旦苗を穴の部分に置いてみるとわかりやすい
- 植え穴に水を注ぐ
- 植え付け後の水やりでは根の真下の部分に水が届きにくいため
- また植え付け後、水を求めて勢いよく根を張ってくれる
- ポットから苗を優しく取り出す
- 根がびっしり回っている場合は、底の部分を少しだけ手でほぐすこともあるが
なるべく触らないほうが根を痛める心配がない
- 根がびっしり回っている場合は、底の部分を少しだけ手でほぐすこともあるが
- 苗を植え穴に入れ、周りから土を寄せ、株元を軽く押さえる
- 接ぎ木苗の場合は、接ぎ木部分が土に埋まらないように
- 実生苗は、斜めに植えたり、深めに植える方法もあり
- 接木苗は深植えにならないように注意
- 支柱をたてる
- 苗の根を傷つけないように、少し離れた場所に支柱をしっかりと立てる
- 苗の根を傷つけないように、少し離れた場所に支柱をしっかりと立てる
- 苗が風で倒れないように、支柱と苗を紐で結ぶ
- 支柱はしっかり、苗には優しく結ぶ
- 支柱はしっかり、苗には優しく結ぶ
- プランターの底から水が流れ出るまで、たっぷりと水を与える
- 植え付け後はプランターの底から水が流れ出るまでたっぷりと水やりし、株を活着させる
- その後は表土が乾いたら水を与える
支柱の立て方3種:おすすめは「ゆるふわ巻き」
支柱の準備
植え付け時に支柱を立て、茎が大きくなる前から誘引しておくと安心です。
簡単に(ストレート):支柱1本
苗のすぐ脇に、1本の支柱を垂直に立て、トマトの茎をそのまま真っ直ぐに育てる方法です。
ベランダの地面に直接置く場合に利用できます。
台の上などに置く場合や、高層階のマンションでは、安定性に欠け風に弱いという弱点があります。
一般的な長い支柱の他に、トマト栽培に適したらせん状の支柱もあります。
初心者さん向け(ゆるふわ巻き):長い支柱で3角形
初心者の方には、3本の支柱を使う方法がおすすめです。
- 1株に3本、長さ150~180cmの支柱を用意
- 3本の支柱の先端近くを紐でしばり、三角形状に
- 支柱をプランターにしっかりと深く差し込む
- 紐を再度調整し、倒れないよう固定
- ミニトマトをゆるやかに湾曲させ、巻きながら誘引していく



ベランダ栽培でも、仕立て方なら、真っ直ぐに育てるよりも茎の長さも確保でき、収量が増えますね。
誘引した茎の重さや、風などにも強く、安定しています。
ゆるめに、ふわっと巻いていけば良いので、取り組みやすいです。
慣れてきたら(しっかり巻き):あんどん支柱〜注意点とリカバリー方法も〜
ミニトマト栽培に慣れてきたら、「あんどん仕立て」にする方法もあります。
あんどん仕立て
リング支柱で支柱同士をつなぎ、株を囲うように支柱を立て、茎を湾曲させてランタン形に育てる方法です。
支柱とリング支柱に沿わせるように茎をぐるぐると誘引していくことで、枝の延びるスペースが増え、収穫量がアップします。
コンパクトなのでプランターを台など乗せるなど、上の方に置くことで根元への熱ダメージも減らせます。移動もしやすく、夏場の夜間に地熱や室外機の熱風から株を守る対策もできます。
あんどん仕立て用に追加できるリング支柱
「茎ポキ」にご注意:茎が折れてしまってもリカバリーできます!
ミニトマトはキュウリなどと違って、茎が硬いので、茎を折らないように慎重さが必要です。
あんどん仕立てへの憧れ:「茎ポキ事件」失敗とリカバリー
私が初めてミニトマトを栽培したときのことです。必要な資材を購入するためにホームセンターへ。
そこにはまるで盆栽のようにコンパクトに「行燈」型に仕立てられたミニトマトのプランターが飾ってありました。
私は、「これこれ!こういう風に育てたいんです!」とお店の方に熱望。すると店員さんはとても丁寧な説明をしてくれました。
話をよくうかがってみると、強く湾曲させるには技術が必要で、やはり初心者にはかなり難しそうでした。
そして「このやり方は、慣れてきた来年にしよう。」と納得。素直に長い支柱3本のやり方にしました。
そして翌年は、願い通りこの仕立て方に挑戦しました!
あんどん仕立ては上に伸ばさない分、横にボテっと広がる感じがあります。葉を欠いて仕立てていかないと、茎葉が重なった部分は風通しが悪くなり、病気のリスクもあります。
そして…何回か茎をポキっと折ってしまいました(汗)
私が見ていた園芸番組でも、ミニトマトの誘引中に出演者が茎ポキ(!?)をされていました(笑)。
適切なリカバリーを
このように、皆さまも誘引に挑戦する中で、茎ポキをしてしまうかもしれません。
でも大丈夫です!
まだ繋がっている部分を全て取ってしまわずに、茎を元の位置に繋ぐようにテープで止めてあげましょう。
意外と、このリカバリー方法で、その後も成長を続けてくれるものです。
このようにミニトマトのあんどん仕立ては、より丁寧なお世話が必要になります。
それでも私は、まさに「行燈」のような形に仕立てることができ、たいへん満足しました(^^)。



私のように失敗しないためには、最初はゆるく巻いて、茎が長く伸びてきたら、ゆっくりとツルを下ろすように誘引していきます。
この場合は少し水が切れた状態が良いため、朝の水やり前や、水分の少なくなった夕方に実行してみましょう。
おろされたツルは、だんだんとしっかりカールされた状態で固まり、丈夫になります。
しっかり巻きは、くれぐれも慎重に、です(笑)。
主茎の仕立て方
ミニトマトは、主に実をつけさせる茎を何本にするかで、仕立て方法が変わります。
以下のように、仕立て方法があります。
1本仕立て
ミニトマトの基本の仕立てです。
全てのわき芽を取り除いて育てます。
一番わかりやすく、初心者の方におすすめです。
2本仕立て
収穫量を増やしたい場合は2本仕立てにチャレンジしましょう。
1本仕立て(主枝1本のみ伸ばす)に比べ、約1.5倍になります。
支柱1本の場合は2本目をそばに立てて、三角形仕立て・あんどん仕立ての支柱はそのまま、3種全てに応用できます。
主枝に加えて第1花房下の強い わき芽をもう1本伸ばして計2本に仕立てます。
基本的に、一番下の花(実)のすぐ下のわき芽だけを残し、それより下のわき芽はすべて摘み取ります。それより上のわき芽も、見つけ次第こまめに取り除きましょう。



2本仕立てのコツは、第一花房のすぐ下のわき芽を残すこと。
2本仕立てで育てると、1本仕立てのおよそ1.5倍の収量が見込めます!
3本以上、多数のわき芽を伸ばす場合
- 横に大きく広がるので、場所を取る
- 集合住宅のベランダでは、鉢数や置き場の検討が必要
その他の仕立て方法:放任(ソバージュ)
主に畑での栽培に向く方法で、以下の仕立て方もあります。
ベランダ菜園では、特に矮性ミニトマト栽培に適しています。
矮性ミニトマト:ベランダ菜園では、「半放任」栽培がおすすめ
ベランダ菜園での矮性ミニトマト栽培は、次のような「半放任」栽培のスタイルが良いでしょう。
- 短い支柱を1〜数本立てる
- わき芽をつまないで育てる
- 茎が垂れてきた場合など、部分的に紐で支柱に結ぶ
畑での放任栽培(ソバージュ栽培)に倣って…
- アイコなど、樹勢の強い品種が向く
- 肥料・微量要素を通常より少し多めに投入すると肥料成分の不足を防止できる
ここからは、ミニトマトの日々の管理方法についてご紹介します。
ミニトマトのプランターの置き場所は:なるべく日当たりの良いところに
日当たりと風通しの良い場所に
- 最低でも半日(4~6時間)以上は直射日光が当たる場所がベスト
- 日当たりが悪いと実付きが悪くなる



矮性ミニトマト、半日陰でも育ちました!
2025年に育てたマンマミーア。
空梅雨・猛暑の影響か、我が家の3〜4時間の日当たりのベランダでも「8号プランター2鉢で89個」とまずまずの収穫ができました。
私にとっては上出来の結果です!
ミニトマトの水やり:水を切らすと甘くなる?
ベランダのプランターでミニトマトを育てていると、「水やりの頻度は?」「水を控えると甘くなるって本当?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
特に初心者さんにとっては、「水をやりすぎて失敗しないか」「控えすぎて枯れないか」など、不安もつきものです。



水を少なめに育てたほうが甘くなるって聞いたんですけど、本当なんでしょうか?



はい、確かにそういった育て方もあります。ただし、タイミングややり方を間違えると、実が割れたり株が弱ったりしますので、最初は「安定した水分管理」をおすすめします。
ここでは、ベランダのプランターでミニトマトを育てる際の、基本的な水やり方法と注意点について、わかりやすく解説していきます。
タイミングや量のコツ、夏場の注意点も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
植え付け直後はしっかりと
苗を植え付けた直後は、根がしっかりと張っていないため、たっぷりと水を与えることが大切です。
初期のたっぷりは、この1回のみです。
生育初期は:控えめに
ミニトマトの生育初期には、以下のように加湿に注意しましょう。
- 水のやりすぎは根腐れの原因に
- 土の湿り具合をよく見て判断
- 水やりは株元へ静かに行う
(苗が若いうちに葉や花に水がかかったり、土の跳ね返りは病気の原因に)
「土が乾いたらたっぷり」が基本のリズム
ミニトマトは過湿に弱い一方で、水切れにも敏感です。
基本のリズムは「土の表面が乾いたら、株元にたっぷり与える」こと。
頻度で決めるよりも、土の状態を目で見て・触って確認するのがコツです。
真夏は「早朝&夕方」1日2回の水やりも
気温が高くなる夏場は、早朝のうちに水やりを済ませておくのがベストです。
日中に水を与えると、温度上昇で根を傷める可能性があります。
また特に暑さが続く場合、朝の水やりだけでは土が乾き切ってしまったり、葉が萎れてしまう場合は、夕方にも水やりをします。
ただし夕方以降の水やりは、蒸れや病気のリスクがあるため注意が必要です。
夕方1回の水やりはあり?:体力優先で考えましょう
とはいえ、私のように(→最近はすっかり早朝覚醒型になりました/笑)「早起きが苦手」な方や「朝は忙しくて水やりできない…」「暑すぎて無理…」という場合、夕方の水やりは完全にNGではありません。
いくつかの注意点に気をつけて行いましょう。
植物への影響
夕方に与える場合は、土の表面が乾いていることを確認。
風通しの良いベランダなら病気のリスクも抑えられます。
また蒸れ防止のために、不要になった下葉の整理など、株元をスッキリさせておくことも重要です。
ご自身の体調・安全面
真夏の水やりは、無理をせずご自身の体調を最優先に。
熱中症を避けるためにも、涼しい時間帯の作業でOKです。育てる側が元気でいることも、家庭菜園ではとても大切なことです。
タイミングや量より「安定した水分管理」が大切
「甘くしたいから水を減らす」という考え方もありますが、初心者さんにはあまりおすすめできません。
急に水を減らすと、実が割れたり、株全体が弱ってしまうことも。
まずは毎日、必要な分を安定して与えることが、失敗しにくく甘い実を育てる近道です。
まとめ:基本は「安定供給」+無理のないタイミングで
「水を控えて甘く」は中・上級者向けのテクニック。初心者さんはまずは安定第一でOKです。
ベランダプランターでは乾燥が進みやすいため、土の状態をこまめに確認しましょう。
真夏の水やりは早朝が理想的ですが、夕方でも適切に行えば問題ありません。



「水を切らして甘くする」という育て方は、主にプロの農家さんがビニールハウス栽培でよく行う方法でもあります。
ベランダ菜園において、水やりの調整が難しいと感じる初心者の方には、極端な水切りはおすすめできません。
ミニトマトのお世話❶:「誘引」で成長をサポート
ミニトマトの茎が伸びてきたら、倒れないように支柱に「誘引(ゆういん)」します。



誘引ってなんですか?



誘引(ゆういん)とは、野菜の茎や枝、つるを支柱やネット、フェンスなどにひもやクリップで固定し、成長方向や形を整える作業です



どんなふうに紐やクリップを使うのかな?



ミニトマトの誘引の方法を説明しますね。
ミニトマトの誘引
ミニトマトの「誘引(ゆういん)」は、茎や枝を支柱やネット、紐などに固定して、植物の成長をサポートし、形を整える大切なお世話の一つです。
誘引の目的・効果
- 倒伏防止
- ミニトマトは茎が長く伸び、実が重くなると倒れやすいため、誘引でしっかり支えます。
- 日当たり・風通しの確保
- 茎や葉が重なり合わないよう整理し、病気の発生を防ぎます。
- 収穫量・品質の向上
- 実が地面につかず、きれいな果実が収穫できるようになります。
- 管理作業の効率化
- 茎や実の位置が分かりやすくなり、収穫や手入れがしやすくなります。
具体的なやり方
- 支柱やネットを立てる
- ひもやクリップで固定する
- 茎と支柱を、紐で8の字になるように、ゆるめに結びます。
- 茎やつるを8の字にゆるく結ぶのが一般的。きつく結びすぎないことが重要です。
- 成長に合わせて定期的に誘引し直す
- 成長に合わせて、20~30cm間隔でひもで支柱に固定し、誘引箇所を増やしていきます。
- 植物が伸びるごとに、こまめに誘引箇所も調整します。
注意点
きつく結ぶと茎の成長を妨げてしまいます。植物の成長を妨げないようにしましょう。
誘引を怠ると、枝やつるが絡み合ったり、倒れて生育不良や病害虫の原因になります。
もしも、誘引中に茎が折れてしまったら、テープでとめてあげましょう。→リカバリーの方法はこちら



結び目はきつすぎず、優しく結んで茎を傷つけないようにするのが、誘引のコツです。
万が一、誘引途中で折れてしまったら、適切なリカバリーを!
誘引は、ミニトマトの成長をサポートし、形を整えるとともに、健康的に育てて、良い実をたくさん収穫するための、大切な基本の作業ですね!
ミニトマトのお世話❷:「わき芽かき」で美味しさを果実に集中!



わき芽をかくとは!?



わき芽かきとは、トマトなどの野菜栽培で、茎と葉の付け根から出てくる新しい芽(わき芽)を摘み取る作業のことです。



どこを摘めば良いのかな?



ミニトマトのわき芽かきの方法を詳しく説明していきます。
ミニトマトの「わき芽かき」とは
主枝(一番太い中心の茎)と葉の付け根から斜めに伸びてくる新しい芽を「わき芽」といいます。
この部分は「側枝」とも呼ばれ、主枝に対して約45度の角度でひょっこりと現れるのが特徴です。
わき芽かきは、ミニトマトの茎と葉の付け根から出てくる新しい芽(わき芽)を摘み取る作業です。わき芽を摘み取ることで、主枝や果実に栄養が集中し、甘くて美味しいミニトマトを収穫しやすくなります。
- 小さいうちに
- なるべく手で摘み取ります。
- 大きく成長してしまった茎にハサミを使う場合は、病気予防のため、清潔なものを使いましょう。
- 下から順に
- 特に下の方のわき芽は大きくなりやすいので、下から順に取っていくと分かりやすいです。
- わき芽を放置すると
- 枝葉ばかりが茂ってしまい、栄養が実に集中しなくなったり、風通しが悪くなって病気の原因になったりします。
一本仕立ての場合、わき芽はすべて摘み取ります。見つけ次第こまめに取り除きましょう。
※矮性のミニトマトなど、放任で育てる品種もありますが、一般的なミニトマトはわき芽かきが必要です。


わき芽かきの目的
- 栄養の分散を防ぐ
- わき芽を放置すると、そちらにも栄養が分散し、実が小さくなったり味が落ちたりします。
- 株の風通し・日当たりを良くする
- 葉や枝が混み合わず、病害虫の発生リスクが下がります。
- 管理・収穫をしやすくする
- 株の形が整い、作業性が向上します。
わき芽かきのやり方
- 基本は手で摘み取る
わき芽の根元を親指と人差し指でしっかり挟み、ポキっとひねるようにすると簡単に取れます。 - 大きくなったわき芽は消毒したハサミで
太くなった場合は、主枝の表皮を傷つけないように注意しながら、清潔なハサミで切り取ります。 - 作業は晴天の日に
切り口が乾きやすく、病原菌の侵入リスクを減らせます。






タイミング・頻度
- 植え付け直後からスタート
苗を植えたら根が活着した頃、最初のわき芽かきを始めます。 - 週2~3回の観察が目安
わき芽はすぐ伸びるので、週2~3回は株をチェックし、小さいうちに取り除くのが理想です。 - 高温期は特に頻繁に
夏場は成長が早いので、こまめな確認が必要です。



晴れた日の午前中がベストです。
無理に手で取ろうとすると、そこから茎が裂けてしまう場合があります。
茎の水分が少なくハリが無い時や、大きくなったわき芽は無理せずに清潔なハサミを使いましょう。
その他のポイント
- 小さすぎると、爪などで茎を傷つける場合も。指で摘むことのできる大きさになってから
- 大きくなりすぎたわき芽は無理に取らず、側枝として仕立てる方法も(2本仕立てなど)
- わき芽かきの際は、手を清潔にしておくことが大切



ミニトマト栽培において、わき芽かきはとても重要な管理作業。
小さいうちに手で摘み取り、こまめに観察して管理しましょう。
ミニトマトのお世話❸:「摘心」でさらに株の充実を



摘心!?また新しい言葉が出てきました。



摘心とは、野菜や草花の茎の先端(頂芽)を摘み取る(切り取る)作業です。
「ピンチ」「芯止め」とも呼ばれます
ミニトマトの摘心について
摘心(てきしん)は、ミニトマトの主茎(中心となる茎)の先端を切り取る作業です。主に、実にしっかり栄養を届ける、樹の高さや管理をしやすくするなどの目的で行われます。
摘心のタイミング
- 支柱の高さに到達したとき
一般的には、主枝が支柱のてっぺんまで伸びた頃が摘心の目安 - 花房の数で判断する方法も
下から数えて5段目など決めておいて、花房の上で摘心 - 収穫時期から逆算する方法も
例えば9月上旬まで収穫したい場合、花が咲いてから約50日で収穫できるので、7月中旬に花が咲いている段を残して摘心する、といった調整も可能
摘心のやり方
- ハサミを使うのがおすすめ
- 成長点(先端)が高い場合や太い場合は、ハサミでカット
- 手が届く場合は手で折り取ることもできる
- 晴れた日に行う
- 傷口が乾きやすく、病気のリスクを減らせる
- 葉を2枚ほど残して摘心
- 花房の上に2枚ほど葉を残して摘心すると、上の葉まで水分や栄養を届けるために、通り道にあたる果実が充実
- 残った葉が屋根代わりになり実を守る
摘心をしないとどうなる?
- 樹がどんどん上に伸び続け、管理や収穫が難しくなる
- 栄養が分散し、実の品質が落ちたり、茎が折れたりすることがある
摘心後の管理
株の成長が止まり、残った実や葉に栄養が集中します。
- 新たなわき芽や葉が出てきたら、適度に剪定して風通しを良くする
- 一番上の花房で実が収穫できたら、その株の栽培は終了



摘心をすることで、実の品質向上や管理のしやすさにつながります。
特にベランダの限られたスペースでは、摘心が重要ですね。
私の場合、8月に入ったら摘心して、プランターの置き場所を移動し、他の野菜に席を譲るようにしています。
ミニトマトの追肥:成長に必要な栄養補給
ミニトマトの実が小豆大(第1花房の実が着果し始めた頃)になったら追肥を始めます。
これ以降は1週間に1回のペースで液体肥料を与えます。
植え付け時に使った培養土の肥料(元肥)の効果は、徐々に薄れていきます。
肥料が不足すると果実が大きくならなかったり、成長が鈍る原因になるので、開花後は必ず追肥を行いましょう。
- 最初の実が小豆くらいの大きさになり始めた頃
(植え付けから約1ヶ月後)
- 1〜2週間に1回程度
- 液体肥料
- 固形肥料(製品の指示に従った量を)株元から少し離れた場所にばらまきます。
肥料の与えすぎは禁物!
・葉ばかりが茂って実が付きにくくなる「つるぼけ」状態になることがあります。
・パッケージの指示量を守りましょう。
ミニトマトの「つるぼけ」とは
つるぼけ(または「木ぼけ」「樹ボケ」)とは、ミニトマトの茎や葉が過剰に生長し、実がつきにくくなる生育障害です。
主な症状としては、茎が太くなり、葉が大きく濃い緑色になり、葉先が内側に丸まることが多いです。この状態になると、花芽がつきにくくなり、実がなっても肥大しにくく、最悪の場合は果実の先端が腐る「尻腐れ」も発生しやすくなります。
つるぼけの主な原因
- 窒素分の過剰
肥料、特に窒素分を与えすぎると、葉や茎の生長が旺盛になりすぎて「つるぼけ」になる - 水分過多
水やりが多すぎると、肥料分が過剰に根に吸収されやすくなり、つるぼけを助長 - 日照不足や着果不良
花がうまく受粉・着果しないと、養分が実ではなく茎葉に回ってしまい、つるぼけが起こることも
つるぼけのサイン
- 茎が太く、葉が大きい
- 葉色が濃い緑
- 葉先が内側に巻く
- 花や実がつきにくい
対策
- 追肥を控える
肥料(特に窒素)の追加をストップし、肥料分が抜けるまで様子を見る - 水やりを控えめに
土が乾き気味になるまで水やりを控え、根からの吸収を抑える - 摘芯や仕立て直し
状況によっては、太くなった主茎を摘芯し、側枝を育て直す方法もありますが、必ずしも効果的とは限らない - 下葉かきや芽かき
不要な葉やわき芽を取り除き、養分の分散を防ぐ - リン酸・苦土肥料の利用
リン酸を多く含む肥料
まとめ
ミニトマトのつるぼけは、主に肥料(特に窒素)や水分の与えすぎが原因で、茎葉ばかりが大きくなり実がつかなくなる現象です。追肥や水やりを控え、リン酸肥料を利用することで改善を図ります。
予防のためには、元肥や追肥の量を適切に管理し、着果の促進や芽かきも重要です。
ミニトマトの人工授粉:通常は無しでOK(必要に応じて実付きを良くするために)
トマトは自家受粉する植物ですので基本的には人の手による受粉作業はいりません。
しかし、ベランダ菜園において風や虫が少ない環境では、受粉しにくいことがあります。
その場合は花が咲いたら、指や筆で花全体を揺らしたり、優しく弾いたりしてあげると、受粉が促され、実付きが良くなリます。
ミニトマトの収穫:ベランダからの直行便!
いよいよ収穫の時が来ました。ベランダから直行のとれたてをどうぞ!


- 開花から約40~50日後
- 実がヘタの近くまで赤く色づいたら収穫のサインです。
- 実が熟したら、ハサミでヘタの少し上の部分を切って収穫
- ヘタの上の少しでっぱった部分に指を当てて、指の方向へ倒すと、手で取ることもできます。
真夏の暑い時期は、完熟まで待っていると、実が割れたり、強い日差しで果焼けを起こすことがあります。
その場合は、少し早めに収穫しましょう。室内で追熟することができます。



採れたての新鮮なミニトマトの味は最高です!
【鳥にご用心:しっかり見られています!】
人間が一番美味しいと感じる熟した頃には、まるでその時を待っていたかのように鳥が狙ってくることがあります。
特に赤くなる品種のミニトマトは鳥に狙われやすいのでご注意!
対策はネットで房ごと覆ってしまうのが有効です。
キッチン用の水切りネット(排水ネット)などを丸ごと実に被せ、上部を洗濯バサミで留めてしまうと鳥除けになります。
収穫期にはネットや不織布で覆うことで、実を守りながら育てることができます。



実が育ってきたら、赤く色づく前に台所用の排水ネットなどを房ごとかけておきましょう。
ミニトマトの実が割れるのはなぜ?:裂果の原因と防ぎ方
ミニトマトが赤く実ってきたと思ったら、ある日パックリと割れていた…。
そんな経験をした方も多いのではないでしょうか。
これは「裂果(れっか)」と呼ばれる現象で、特にプランター栽培やベランダ栽培では起きやすいトラブルのひとつです。



せっかく実がついたのに、皮がパックリ割れてしまって…。水が多すぎたんでしょうか?



裂果の主な原因は「水分の急な変化」にあります。
今回はその理由と、ベランダでもできる対策をご紹介します。
裂果とは?皮が割れる生理現象
裂果とは、実の皮が割れてしまうこと。
ミニトマトの果実は、水分を急激に吸収すると中身だけがふくらみ、皮がそれに追いつけずに裂けてしまいます。
- 多くは収穫間近の熟した実に発生
- 種類(品種)によっても、裂けやすさに差がある
- 気温・湿度・水分量などの影響を受けやすい
- 「柔らかさ」が特徴の品種に起こりやすい(プチぷよなど)
小さなヒビ程度で済むこともありますが、割れた部分から傷みやすくなったり、カビが入ったりするリスクもあります。
主な原因は「乾燥 → 急な吸水」の変化
裂果の最も多い原因は、水分環境の急激な変化です。
特に「乾燥した状態が続いたあとに急に大量の水を吸う」と、裂けやすくなります。
具体的な例:
- 数日水を控えていた → 一気にたっぷり水やり
- 雨が降ってプランターに水が入りすぎた
- 雨どい・エアコン室外機などから水滴が繰り返し落ちていた
ミニトマトの皮は丈夫なようでいて、急な変化にはとても敏感です。こまめな観察と、急激な環境変化を避ける管理がポイントです。
雨対策も重要|ベランダでも油断しないで
裂果は水やりだけでなく、雨でも起こることがあります。
特にベランダ栽培では、思っている以上に風雨の影響を受けることも。
対策のポイント:
- プランターに直接雨が当たらないように配置する
- 簡易の雨よけシートやフレームを使う
- 通常の雨なら、防虫ネットや遮光ネットを使用してもある程度は防げます。
- 雨の後は、プランター内の水はけをチェック
雨の後に「実が一気に割れた」という例も多いため、物理的に雨を避ける工夫が効果的です。
裂果を防ぐ水やりのコツは「安定した管理」
裂果を避けるには、「水をあげる・あげない」という極端な管理ではなく、安定した水分の維持が大切です。
安定管理の基本:
- 土を乾かせすぎない
- 天気・温度を見ながら、水やりを調節
- 夏場はプランターの乾燥が早いため、こまめな観察を
一度に与える水の量を極端に変えないことも大切です。「控えて→一気に」ではなく、毎回プランターの土の水分量がほぼ同じになるように意識しましょう。
割れてしまった実はどうする?
割れてしまった実は食べられる場合が多いですが、早めの処理が必要です。
- ヒビ程度ならそのまま収穫して早めに食べる
- 酢漬けやトマトソースなどの加熱調理にも最適
- 完全に裂けたものは虫・カビが入りやすいので早めに処分を
見た目は少し残念でも、味は変わらないことがほとんど。
しっかり収穫して、美味しく活かしてあげましょう。



裂果のしやすさは品種による影響もあります。
安定した水分を保ち、「水やりの量」や「雨対策」で実割れを防止しましょう。
ミニトマトの撤収:栽培終盤の管理
8月に入ったら撤収の準備に入ります。
近年、日本の夏は非常に高温になるため、8月を過ぎるとミニトマトの着果率が著しく低下します。高温下では花が咲いても実になりにくいため、ベランダなど気温が高くなる環境では8月上旬~中旬頃までに撤収するのが一般的です。
ベランダでは先行逃げ切り型で、早めの撤収がおすすめ
真夏の高温下でのミニトマトは、花が咲いたとしても実がつきづらく、実がついてもよい実にならないことが多いです。
私のベランダでは、8月になるとミニトマトは一気にサビダニにやられてしまいます。
私の経験上、対策をして一時的に持ち堪えたり、脇芽で栽培を続けたとしても、プランターが根詰まり、株が老化していて、秋にかけては生育が良くありませんでした。
少し涼しくなって、花が咲き実ができても、温度不足でその後なかなか赤く熟すまでに至らず…
なので、秋冬野菜の栽培も考えて、8月で上座を降り、次の野菜に場所を譲ってもらっています。
ミニトマトは少し日陰に移動し、水やりはしっかり続け、それまでについていた実を収穫できるサイズまで育てるようにします。
なかなか熟してこない場合には、青いまま収穫し、部屋の中に数日置いて追熟させます。
それでも赤くならないミニトマトは、マリネにしたり、火を通して食べやすく調理していただくようにしています。
青いミニトマトを生で食べるのは注意!
ミニトマトを青い状態(未熟な状態)で食べるのは注意が必要です。
青いトマトには「トマチン」という毒性成分が含まれており、これはジャガイモの芽に含まれる「ソラニン」と似た成分です。
- トマチンの含有量は未熟なほど多く、完熟するにつれて減少します。
- 通常の料理に使う程度の量なら急性中毒など重大な健康被害は起こりにくいとされていますが、未熟すぎる実を大量に食べると食中毒(めまい、ふらつき、吐き気など)を起こす可能性があります。
食べる時の注意点
- 青いミニトマトを生食するのは避けましょう。
ジャガイモのα-ソラニンやトマトのα-トマチンは有毒なステロイドグリコアルカロイド(SGA)であり、SGAは幅広い生物に対して毒性を示すため天然の防御物質として機能している。
- 食べる場合は加熱調理(ピクルスや炒め物など)を推奨します。
- 基本的には完熟させてから食べるのが安全です。



ミニトマトは実(じつ)は暑さが苦手。早期栽培を切り上げ、秋冬野菜の栽培に切り替えるのがよいですね。
青い状態で収穫したミニトマトは、室内で追熟・調理するなどして、いただきましょう。
その他トラブルシューティング:困ったときは?
- 実がつかない、花が落ちます
-
日照不足、肥料の与えすぎ、水切れ、高温も原因です
置き場所や肥料、水やりを見直しましょう。
栽培終盤は、株の老朽化も考えられます。 - 皮が硬いです
-
強い日照や高温で一気に熟したり、肥料過多、水不足などが原因です
皮の硬さの原因は、プラム型など、品種による影響も大きいです。(アイコ、フラガールなど)
完熟させてから収穫すると、あまり気にならないことも。 - 葉に白い粉、黒いシミがあります。
-
カビなどの病気が考えられます
風通しを良くすること(わき芽かき、葉が茂りすぎたら少し葉を落とす)、泥はねを防ぐことが予防になります。
病気になった葉は早めに取り除きましょう。 - ミニトマトに穴が開いています
-
タバコガによるものです
近くに糞が落ちていないか確認しましょう。発見次第、取り除きます。
果実は摘果します。
大量発生した場合は、食品成分由来の安全性の高い忌避剤の使用も検討します。 - もっと小さい虫がついています
-
アブラムシ、ハダニ、サビダニなどです
こまめに葉の裏などをチェックし、見つけたらすぐに手で取り除くか、水で洗い流します。
大量発生した場合は、食品成分由来の安全性の高い忌避剤の使用も検討します。
まとめ:手間をかけた分だけ、感動も大きい!
ミニトマト栽培は、植え付けから収穫まで、日々成長を見守る楽しさがあります。
誘引やわき芽かき、追肥など、少し手間はかかりますが、その分、真っ赤な実を収穫できたときの喜びはひとしおです。
ぜひこの記事を参考に、ベランダでのミニトマト栽培にチャレンジして、採れたての美味しいミニトマトを味わってみてください!
きっと素敵なベランダ菜園ライフが待っています。
ミニトマトの栽培カレンダー
| 月 | 主な作業内容 |
|---|---|
| 4月 | 暖かい時期を見て苗の植え付け。プランター準備(土作り・鉢底ネット・石)、支柱設置。植え付け後はたっぷり灌水。 |
| 5月 | 定植した株の管理。支柱に誘引、下のわき芽を摘む。第1花房に果実が着き始めたら追肥を開始。 |
| 6月 | 花芽・実つきが活発化。わき芽かきと水やりを習慣に。2~3週に1回追肥し、1房10~15果に摘果しながら収穫開始。 |
| 7月 | 収穫ピーク。梅雨明けや前線に備え雨除けを設置。高温対策に遮光ネットやプランターを台上に。伸びすぎた主枝は摘心。 |
| 8月 | 栽培終了。秋冬野菜を育てる場合はここで場所を譲る。続行するなら整枝・摘心・追肥を続ける。 |
| 9月 | 気温次第では継続収穫が可能。日照と温度を確保できれば小粒でも果実は実る。 |
| 10月〜 | 栽培完全終了。プランターを片付け、土の再生または入れ替え。支柱やネットは洗って保管。 |
参考・引用文献(2025年4月参照)
種苗法(平成十年法律第八十三号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000083
農林水産省「品種登録データ検索」
https://www.hinshu2.maff.go.jp/vips/cmm/apCMM110.aspx?MOSS=1
公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「流通品種データベース」
https://hinshu-data.jataff.or.jp/varieties/search?clear=1
大阪大学ResOU「ジャガイモやトマトの毒を作り出す鍵酵素を発見」
https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2024/20241224_3(2024年12月)
























